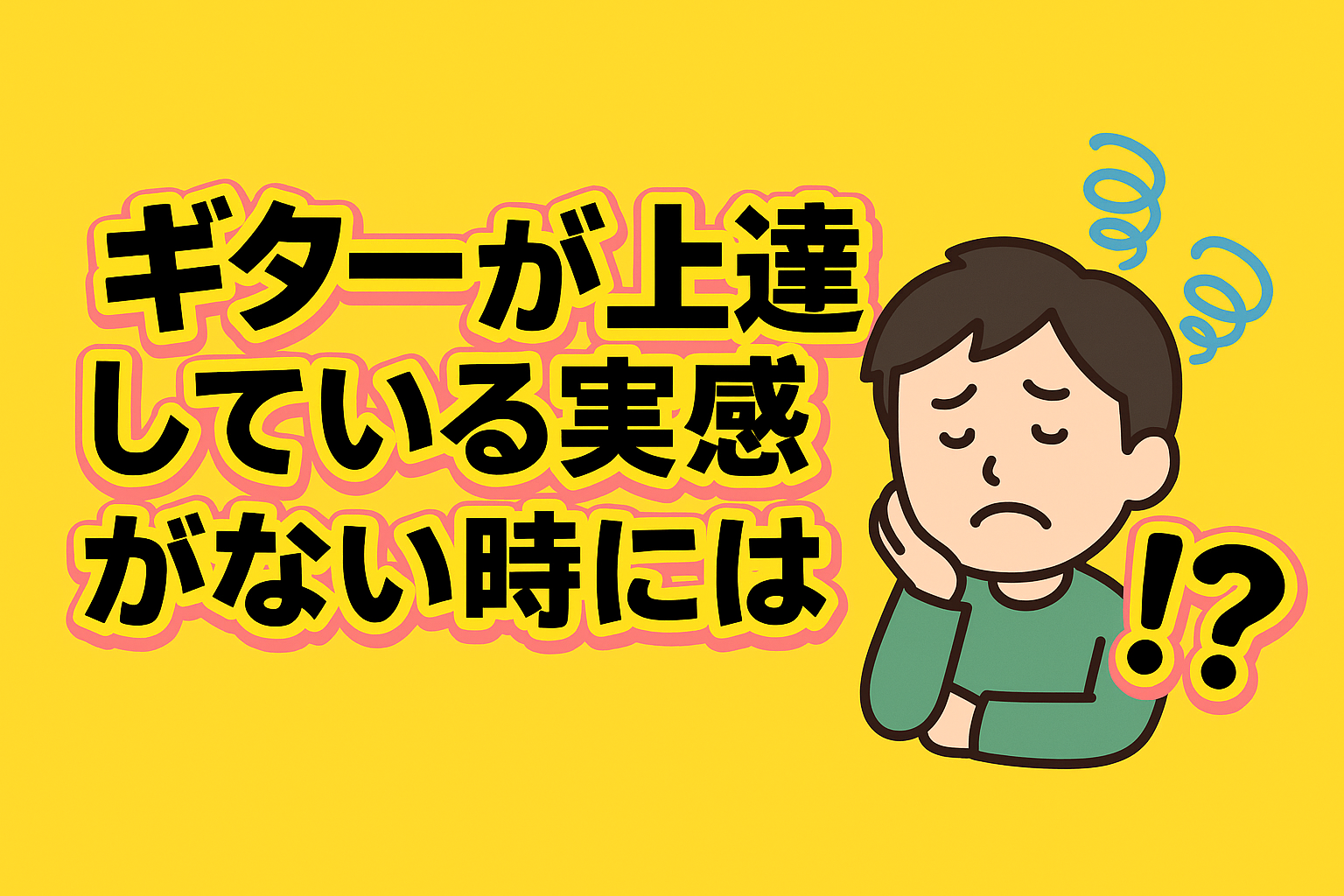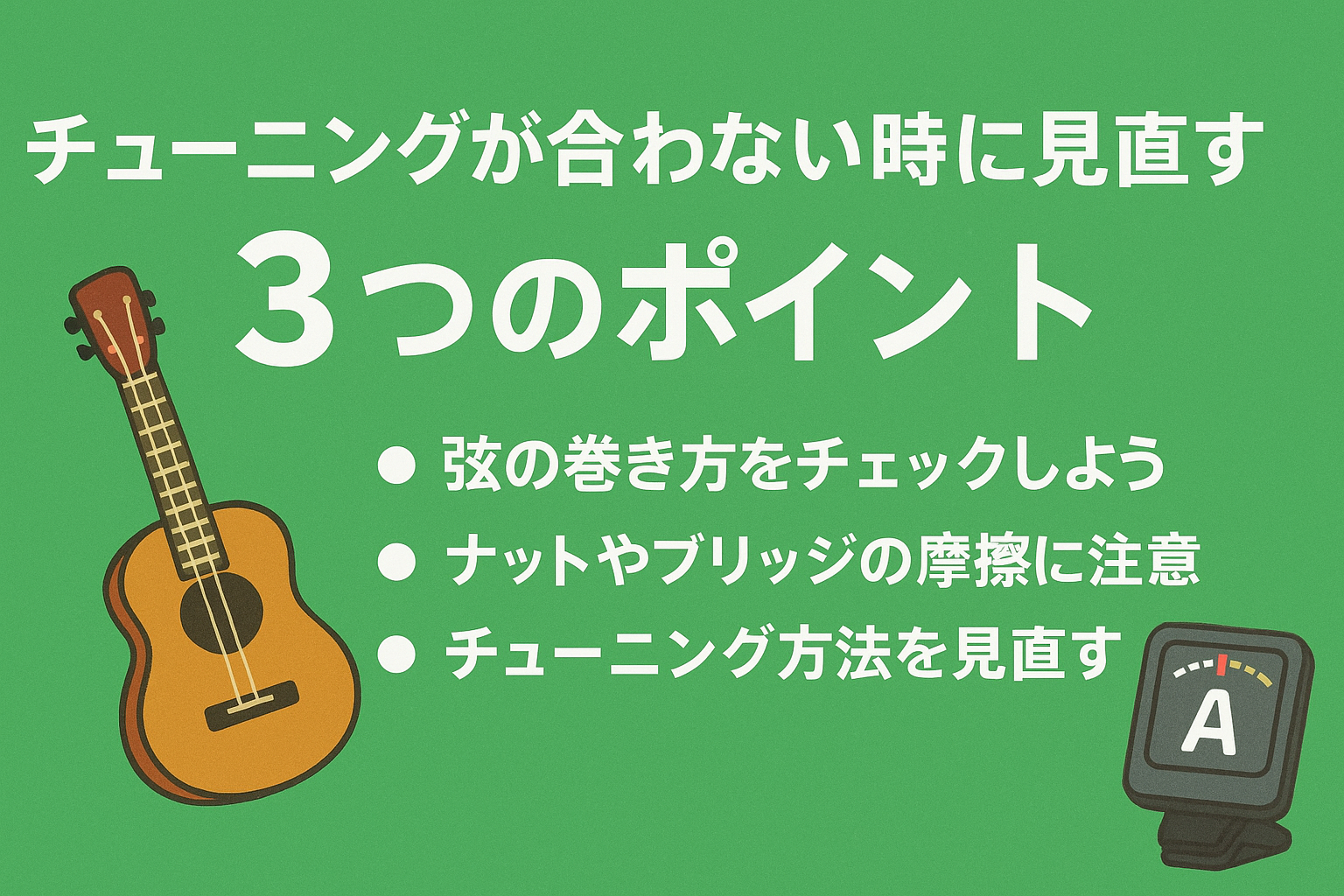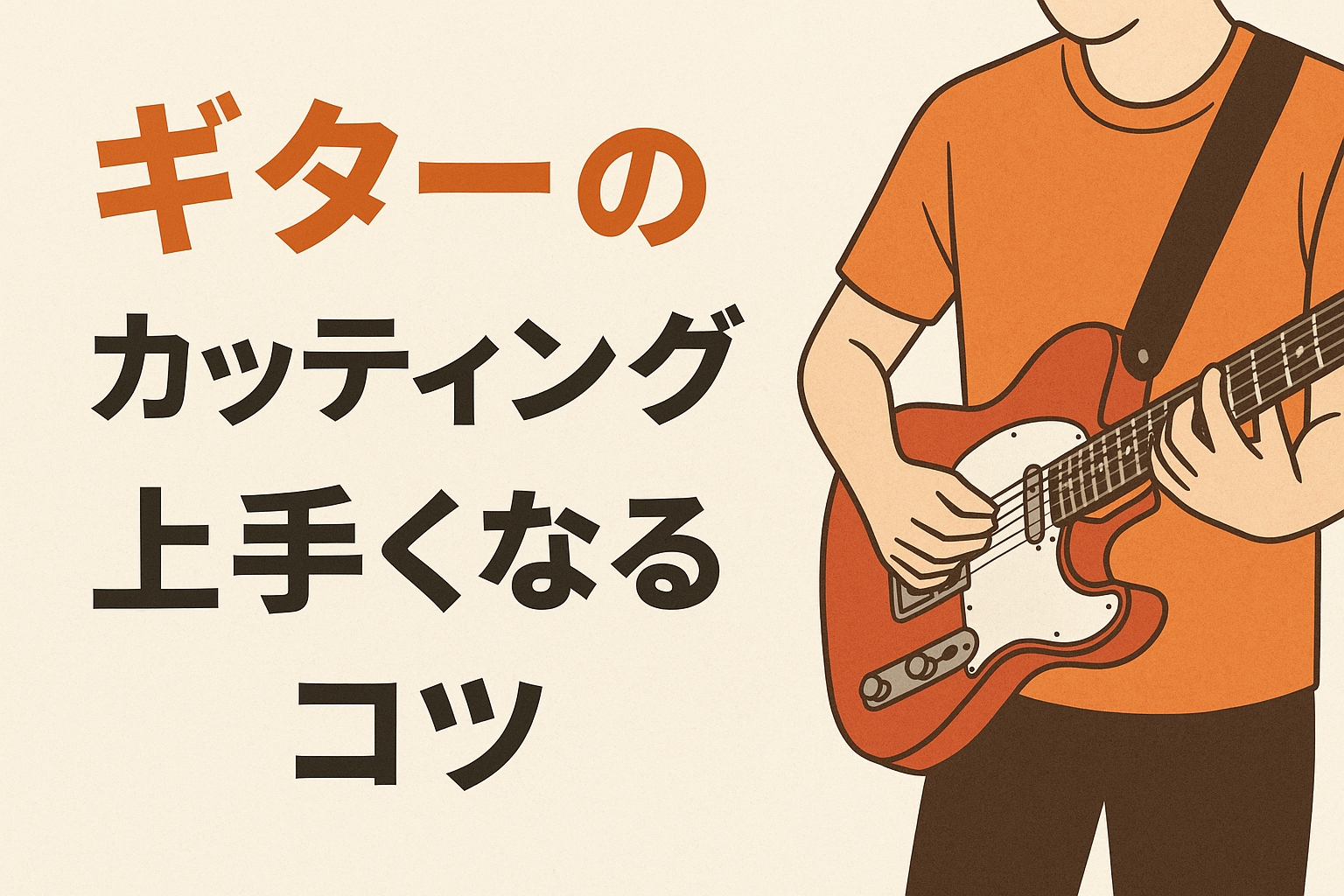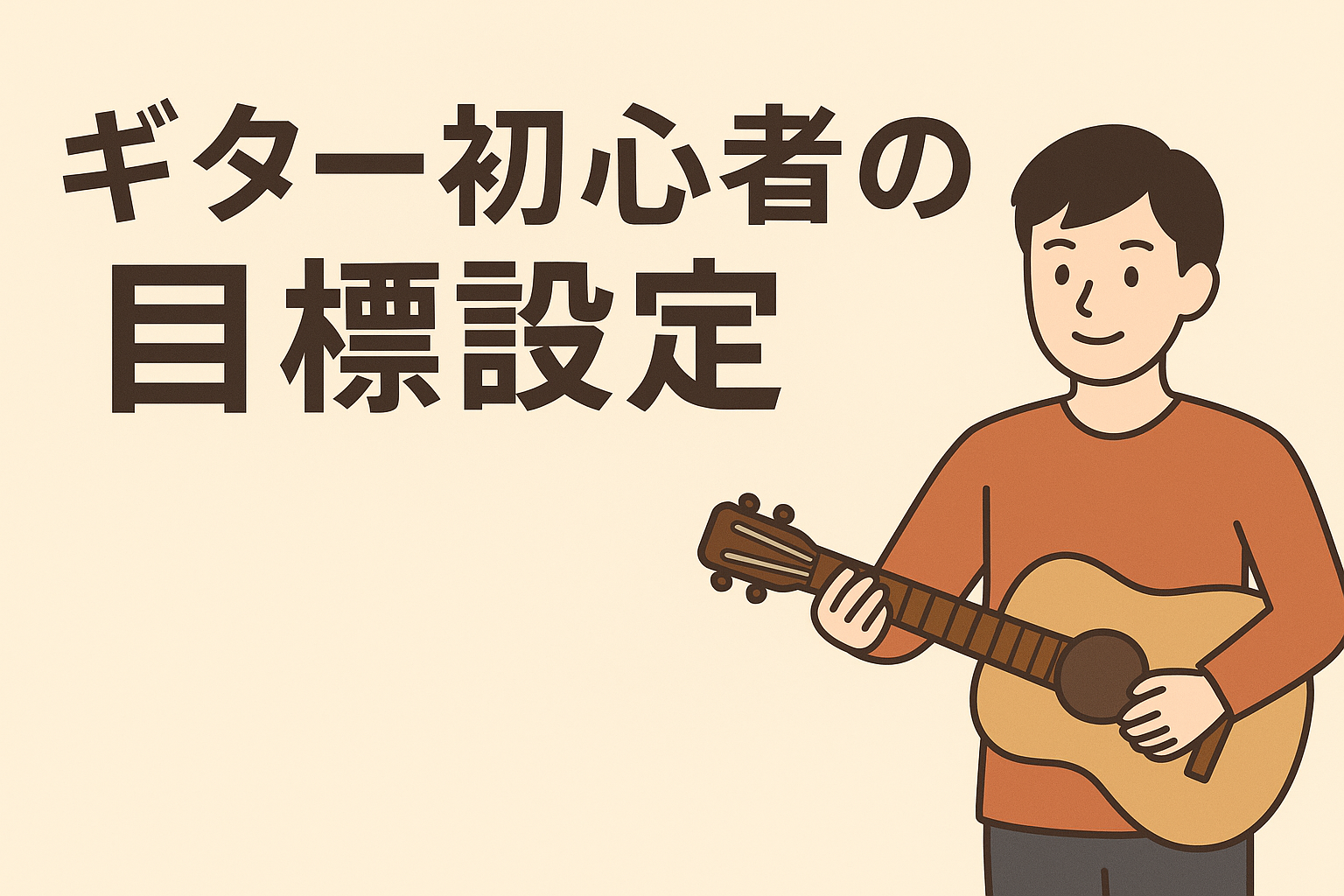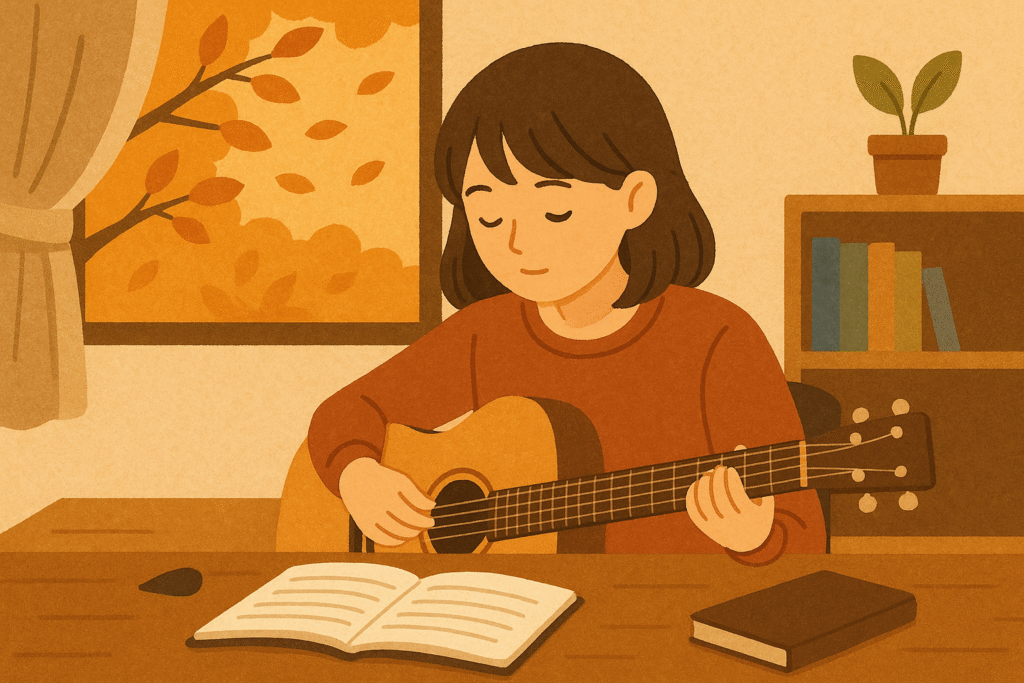① ギターアンプ
エレキギターはアンプに繋がないとほとんど音が出ません。
自宅用なら10W程度の小型アンプでOKです。
最近はBluetooth接続やエフェクト内蔵の便利モデルもあるので、ネットやお店で見比べて購入しましょう。
② シールド(ケーブル)
ギターとアンプを繋ぐケーブルです。
自宅用であれば長さは2〜3mくらいが使いやすいでしょう。
③ チューナー
ギターは弾く前に必ずチューニングが必要。
初心者にはクリップ式、ペダル式チューナーが簡単で見やすいと思います。
スマホアプリでも代用できますが、感度・精度は専用チューナーのほうが上です。
④ ピック
弦を弾く道具です。厚みやサイズ、素材で弾き心地がかなり変わります。
最初はミディアム(中くらいの厚さ)のものを数枚買い、その後いろいろ試しつつ自分に合うピックを探しましょう。
自分の好きなアーティストのシグネチャーモデルがあれば試してみるのも面白いですね。
⑤ ストラップ
立って弾くときだけでなく、座っていてもギターの安定感UP。
長さ・素材も色々あるので試してみましょう。
⑥ ギタースタンド
ギターを壁に立てかけると倒れる危険があるので、専用スタンドは必須です。
折りたたみ式や壁掛けタイプもあります。置ける環境に合わせたものを探してみましょう。
⑦ ソフトケース or ギグバッグ
ギターの保管や持ち運び用。
購入時に付属しているものにはクオリティがあまり良くないものもあるので、軽くてクッション性が良いものを別途購入すると安心です。
⚡ マストではなくてもあると便利!快適・効率アップアイテム
- ヘッドホン
夜間の練習やアパートでも気にせず音が出せるようになります。まずアンプにヘッドホンジャックがあるか確認しましょう。 - メトロノーム
リズム感はギター上達に欠かせません。
スマホアプリでも代用可できますが、クリック音や視認性は専用のものがベター。 - クロス(布)
弦やボディについた汗や指紋を拭くだけでサビや劣化を防止。練習後にサッとひと拭きすることを習慣付けましょう! - 替え弦(スペア弦)
弦は突然切れることがあります。1セットは必ずストックしておくと安心です。
最初のうちは「09-42」「10-46」などの細めのゲージが指の負担が少なくおすすめ。 - カポタスト(カポ)
まだコードが少ししか弾けなくても、カポがあれば好きな曲が弾きやすくなります。
必須ではありませんが、曲の幅がぐっと広がるかもしれません。
🧰 メンテナンス道具も忘れずに!
- 弦カッター(ニッパー):弦交換時に必要です。
- 六角レンチ:弦高調整などのために。ギターに付属している場合もあります。
クオリティを気にしなければ100均でも手に入ります。
余裕があればクリーナーやレモンオイルも!
最初から全て完璧に揃えられなくても大丈夫です。
必要なものから、無理なく順番にゲットして楽しいギターライフを送りましょう!